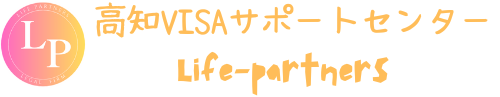「高度専門職ビザ」とは、日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材(高度外国人材)に認められる在留資格です。
高度専門職ビザにおいては、学術研究、経営、技術といった分野ごとに、学歴、職歴、年収や研究実績などにポイント制を導入し、在留の優遇措置が講じられます。
ここでは、「高度専門職ビザ」について、どのような場合に取得することができる?、どうやって申請する?、といった疑問にお答えします。

【このページの要点】
- 高度専門職ビザは、4つに区分される
- 在留期間は、高度専門職1号は5年、2号は無制限
- 高度専門職1号で3年間在留すれば、2号への変更が可能
- 高度専門職ビザ申請の流れ
- 高度専門職ビザ申請に必要な書類
高度専門職ビザとは
「高度専門職ビザ」とは、日本の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材(高度外国人材)に認められる在留資格です。
「高度専門職」の在留資格については、平成26年の「高度人材外国人の受入れの促進等を図るための出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」によって、高度専門職1号イ、1号ロ、1号ハ及び2号の4つに区分されており、2号を除き高度専門職ビザを取得し在留する外国人が、別の区分の職に就こうとする場合には、ビザ変更許可(在留資格変更許可)を受けなければなりません。
高度専門職1号イ・1号ロ・1号ハ
高度専門職2号
ここで、よく混同されがちな「ビザ」と「在留資格」について、説明をしておきます。
「ビザ(査証)」とは、外国にある日本の大使館や領事館がパスポートをチェックし、日本への入国は問題ないと判断した場合に発給されるもので、日本への入国に関する認定の裏書をさします。ただし、日本への入国にあたってこの「ビザ」は必要なものですが、実際に上陸を許可するか否かは、日本の空港や港で上陸時に行われる上陸審査の際に入国審査官が決定します。入国審査官はパスポートに貼られたビザを確認し、上陸を許可するのであればビザに見合った「在留資格」を付与して外国人を上陸させることになります。その時点で「ビザ」は使用済みとなり、上陸時に与えられた「在留資格」が上陸後の外国人が日本に在留する根拠となります。
また、「ビザ申請」と国内で一般的にいわれるものについては、正確には「在留資格認定証明書交付申請」のことを指します。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する、当該外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合すると判断した証明書をいいます。この証明書を事前に取得し、在外公館でビザ発給を申請する場合、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているとして扱われるため、ビザの発給が迅速に行われることとなります。外国人の入国の大半はこの方式を利用しています。
在留資格認定証明書交付申請は、当該外国人、又は、行政書士、弁護士などの代理人が、当該外国人の居住予定地を管轄する出入国管理局(支局・特定の出張所を含む)に申請書を提出して行います。
ただし、本サイトでは、特に断りの無い限り、「在留資格認定証明書交付申請」については一般的な呼称である「ビザ申請」という言葉で言い表します。
家族滞在ビザの要件
以上のように、家族滞在ビザは、①「一定の在留資格」をもって日本に在留する外国人から、②「扶養を受ける」③「配偶者又は子」が④「日常生活」を送ることができる在留資格のことをいいますが、ここでは、ビザ取得の要件となる①~④について詳しく解説します。
①扶養者の「一定の在留資格」
出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)は、別表第1の4の家族滞在の項下欄において、「家族滞在」の在留資格該当性にてついて、「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」と規定しています。
家族滞在ビザを申請しようとする者の扶養者の在留資格もここに規定されているわけですが、具体的には、扶養者は「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、「文化活動」又は「留学」の在留資格をもって滞在する者であることが要求されています。
「外交」及び「公用」の在留資格を有する外国人の扶養を受ける配偶者と子が家族滞在ビザの対象から除かれているのは、「外交」及び「公用」ビザでの活動そのものに、「同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」が含まれているからです。
「特定技能1号」、「技能実習」及び「研修」が除外されているのは、これらの在留資格における活動内容の性格から、家族の帯同を認めないとする方針がとられていることによります。
また、「短期滞在」の除外理由は、通常、観光などで滞在する者の家族も同じく短期滞在ビザを取得し行動を共にするであろうという趣旨です。
②「扶養を受ける」の意義
扶養を受ける者であることが要件とされているのは、入管法が、自ら就労しその収入によって生活できる者は、家族としてではなく日本において就労活動を行う外国人としてその受入れの可否を決することを原則としていることによります。
「扶養を受ける」と言い得るための前提としては、扶養する側すなわち家族滞在ビザの取得を希望する者の配偶者又は親に、扶養する意思と扶養する資金的能力が必要です。この扶養能力の存否に関する判断には、本国にいる扶養家族の人数なども考慮され、特に扶養する者が「留学」や「文化活動」等の在留資格で日本に在留する場合は、家族滞在ビザの取得を希望する者の在留期間中確実にその生活費を支弁し得ると認められる必要があります。
そして、「扶養を受ける」とは、扶養を受ける必要があり又は現に受けているという意味です。配偶者にあっては原則として扶養者である配偶者と同居し、経済的に依存していること、子にあっては扶養者である親の監護養育を受けている状態をいいます。よって、経済的に独立している配偶者や子は、家族滞在ビザの取得はできませんが、20歳以上の子であっても学生であって親の扶養を受けている者には家族滞在ビザが認められる場合があります。
③「配偶者」、「子」の意義
「配偶者」は、婚姻が有効に存続している者に限られ、相手方が死亡した者や離婚した者は含まれません。また、法律上の婚姻関係が成立していても、同居や相互協力といった社会通念上夫婦と認められ得る実体のない場合には、家族滞在ビザにおける配偶者に該当しません。
また、内縁の配偶者、外国で有効に成立している場合であっても同性婚や一夫多妻婚といった婚姻関係を有する者も、家族滞在ビザにおける配偶者に該当しません。
「子」には、嫡出子のほか、普通養子、特別養子、及び認知された非嫡出子が含まれます。成年に達した子も含まれる点において、実子以外では特別養子しか認められない「日本人の配偶者等」ビザ、6歳未満の養子しか認められない「定住者」ビザと異なります。
なお、「配偶者」及び「子」以外の家族は、家族滞在ビザを取得することはできません。よって、「高度専門職」以外のビザを有する者が母国の親を日本に呼び寄せたい場合は、「短期滞在」ビザで呼び寄せた後に、「特定活動」(告示外特定活動)ビザに在留資格を変更する方法によることとなります。
④「日常的な活動」の意義
「日常的な活動」には、家事に従事する活動のほか、教育機関において教育を受けるすなわち学校に通う活動も含まれますが、就労するには資格外活動許可を得るか、就労ビザを取得する必要があります。家族共同体の一員として扶養を受けつつ就労する場合には資格外活動許可の取得を、扶養の必要が無いほどの収入を得る職に就く場合には就労ビザへの変更を行うべきです。
なお、家族滞在ビザは、原則として、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って認められる在留資格です。もっとも、扶養者である配偶者又は親が単純出国をした場合にも、法理論上は、即座に不法滞在となるわけではなく、家族滞在ビザの在留期間の満了までは、ビザが取り消されない限り、日本に在留することが違法となることはありません。これは、「一度為された行政処分は、それが取り消されるまでは形式上有効である。」という行政処分の公定力からの帰結であるといえます。ただし、在留資格該当性が消滅した状況での在留は、在留状況不良と評価されるべきものである以上、家族滞在ビザから他のビザに変更申請をする場合に不利益に考慮される事情ともなることから、実務上は、ビザ変更申請など必要な対応をすべきだと考えられます。
また、家族滞在ビザで在留する者の扶養者である配偶者又は親の在留期間更新許可申請が不許可となり、申請内容変更申出により、出国のための「特定活動」(告示外特定活動)ビザに在留資格を変更することとなった場合には、「家族滞在ビザ」の在留期間更新許可申請を同時申請していた配偶者又は子についても、出国のための「特定活動」(告示外特定活動)ビザに在留資格を変更することとなります。
家族滞在ビザのその他要件審査のポイント
家族滞在ビザを申請する者が、扶養者の子である場合、子が未成年であっても、年齢が高くなるにつれ、日本における活動目的が就労であると認定されたりすることが多くなってきます。
また、扶養者が先に来日して、数年たってから子を呼び寄せる場合にも、日本における活動目的が就労であると認定されたりすることが多くなってきます。扶養者が数年たってから子を呼び寄せる場合には、今までなぜ母国で別の者が監護養育していたのか、また、なぜ今日本に呼び寄せ、扶養者が監護養育する必要が生じたのか等を合理的に説明する必要があります。
家族滞在ビザ申請の流れ
申請者がまだ日本に入国していない場合には、扶養者が出入国在留管理局にビザ申請書(在留資格認定証明書交付申請書)を提出し、許可(在留資格認定証明書の交付)を受けた後、外国の申請者にこの証明書を郵送、証明書を受け取った申請者は日本大使館等で査証発給を受け、日本に入国します。
令和7年7月における、家族滞在ビザ新規申請に関する審査平均期間は、85.5日となっています。
申請を行うまでの書類準備などにも時間を要しますので、お急ぎの場合は、専門家に依頼することも検討されることをお勧めします。
申請人が外国にいる状況での流れは以下のとおりです。
申請に必要な書類の収集
家族滞在ビザの申請には、扶養者と申請者の身分に関する書類、扶養者の収入に関する証明書、納税証明書等多くの書類が必要になります。
出入国管理局に永住ビザ申請
申請者の予定住所地を管轄する出入国管理局の窓口で申請します。
申請取次者として出入国管理局の承認を受けた行政書士・弁護士は申請を取り次ぐことができます。
許可
審査には3か月の期間を要します。交付された在留資格認定証明書を申請人に送付します。
査証発給
日本から送付された在留資格認定証明書をもって、申請人は日本の在外公館に査証の発給を申請します。
査証の発給を受けて、3か月以内に日本に入国します。
入国
在留が3か月以上になる場合は、入国後14日以内に、住所地の市区町村役場に住民登録が必要です。
家族滞在ビザ申請に必要な書類
家族滞在ビザに係る在留資格認定証明書交付申請を行う場合、出入国在留管理局に以下の書類を提出することが必要です。
【家族滞在ビザ申請を行う場合に必要な書類一覧】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
※申請3か月以内に正面から撮影されたもので、無帽・無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。 - 返信用封筒
※定型封筒に宛先を明記の上、返信用切手(簡易書留用)を貼付したもの。 - 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分を証する文書
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)出生証明書(写し)
(5)上記(1)~(4)に準ずる文書 - 扶養者の在留カード又は旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
ア 在職証明書又は営業許可証明書の写し等(扶養者の職業が明らかとなる証明書)
イ 市区町村役場発行の課税証明書及び納税証明書
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
ア 扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
イ 上記アに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
最後に
以上、家族ビザについて、その内容とビザ申請方法、申請における留意点を解説しましたが、出入国在留管理局に対して行うビザ申請には多くの書類の添付が必要であり、また補足説明資料なども必要となってきます。
一度不許可となると再申請はその分ハードルが上がる傾向にもありますので、ビザ申請に不安がある方は、専門家に相談することも検討されることをお勧めします。
当事務所では、家族滞在ビザを申請されるお客様のビザ申請を代行する>ビザ申請サポート(各種身分系)をご用意し、お客様のビザ申請を全面的にサポートするサービスを提供しております。
無料相談にて、家族ビザの許可取得が可能か、また、問題点がある場合にどの程度是正ができるかのアドバイスをさせていただきます。
無料相談は、①電話、②メール、③オンライン(Zoom、Line等)、④来所、⑤ご自宅訪問のいずれかでご対応しております。まずは、お気軽に、お電話かメールでお問合せください。
無料相談はこちら
\
他にご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽に
お問い合わせください!
/

.png)
この記事の執筆者
高知VISAサポートセンター所長
森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士、宅地建物取引士
私も、イギリス在留中には、フラット(アパート)を借りる際をはじめ、多くの現地の方にたくさんお世話になりました。
当事務所では、ビザ申請に関すること以外にも、外国籍の方の行政手続き・不動産・日常生活に関する様々なお困りごとにも相談対応が可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
- 主な担当業務
外国人のお客さまのビザ申請に関するサポートのほか、外国人を雇用する企業様の法的サポートを提供しています。 - Profile
1993年 3月 高知県立追手前高校 卒業
1993年 4月 立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
入管申請取次行政書士(行ー192025200024)
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号