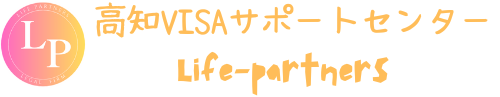「特定技能ビザ」とは、一定の専門性・技能を有する外国人材が、人材確保が困難な産業分野において就労することを可能とするため、平成30年出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)の改正により創設された在留資格です。
特定技能ビザによる就労が許されるのは、特に人材確保が困難な産業分野に限定されており、ここでは、「特定技能ビザ」について、どのような場合に取得することができる?、どうやって申請する?、といった疑問にお答えします。

【このページの要点】
- 人材確保が困難な特定の産業分野に限り、特定技能ビザによる就労が可能。
- 特定1号ビザの技能要件:①技能試験及び日本語試験に合格すること、②又は技能実習2号を良好に終了したこと
- 特定技能2号の技能要件:技能水準の証明のあること(日本語水準の証明は不要)
- 特定技能ビザ申請の流れ
- 特定技能ビザ申請に必要な書類
特定技能ビザとは
特定技能とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的に、平成30年出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)の改正により創設された在留資格です。
上記の制度趣旨からいうと、特定技能ビザの対象は、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人であり、主としていわゆる非熟練業務にあたらせるために外国人を招へいするためのビザではありません。
しかし、実態として日本人の熟練職人等であっても一切の非熟練業務を行わないという職場は限りなく少なく、主たる業務に付随する非熟練業務をこなすことは全面的に禁止されるものではありませんので、特定技能ビザの活用により外国人雇用に取り組む雇用主にあっては熟練業務と非熟練業務の比率の調整を含めて受入れ環境の整備を行う必要があるでしょう。
1号と2号に区分される
特定技能ビザは、要求される技能の熟練度によって、特定技能1号と特定技能2号に区分されています。
特定技能1号については、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」への従事が、特定技能2号については、「熟練した技能を要する業務」への従事が予定されるものです。
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い熟練度を持つ者に付与されるビザですが、特定技能2号に相当する技能を有しているか否かの測定は試験等によって行われ、特定技能1号から特定技能2号に自動的に移行するというような制度設計にはなっていないことに注意が必要です。なお、試験等に合格することによって、特定技能2号に要求される技能水準を有していることが認められれば、特定技能1号を経ることなく、特定技能2号ビザで就労することが可能となります。
在留期間
なお、在留期間の上限については、特定技能1号は通算して5年間であるのに対し、特定技能2号では通算在留期間に制限がありません。
以下に、特定技能1号及び特定技能2号の概要を紹介しておきます。
【特定技能1号の概要】
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了した者は免除) |
| 日本語能力 | 試験(N4等)で確認(技能実習2号を修了した者は免除) |
| 在留期間 | 1年を超えない範囲で更新(通算5年まで) |
| 家族の帯同 | 基本的に認められない |
| 支援 | 受入れ機関又は登録支援機関の支援が必要 |
【特定技能2号の概要】
| 技能水準 | 試験等で確認 |
| 日本語能力 | 試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)除く) |
| 在留期間 | 3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし) |
| 家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 支援 | 受入れ機関又は登録支援機関の支援の対象外 |
なお、特定技能1号については、受入れ機関(雇用主)又は登録支援機関による生活関連支援が必要ですが、この登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う出入国在留管理庁に登録された団体をいいます。
特定技能ビザで就労できる産業分野
特定技能ビザでどのような仕事に就労できるかについては、「生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野」での人材確保という制度創設の趣旨から、対象産業分野が法令により限定されていますので、以下の一覧をご覧ください。
【特定技能1号の対象分野】2025年9月時点
| 分野 | 技能試験 | 日本語試験 | 従事する業務 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 介護技能評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) (上記に加えて)介護日本語評価試験 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付 随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)令和7年4月21日、介護分野の上乗せ基準告示の改正により、訪問系サービスへの従事が可能に |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) | ・建築物内部の清掃 |
| 工業製品製造業 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 〃 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫 製 |
| 建設 | 建設分野特定技能1号評価試験等 | 〃 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 | 〃 | ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器 |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能1号評価試験等 | 〃 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 |
| 航空 | 航空分野特定技能1号評価試験 | 〃 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
| 宿泊 | 宿泊分野特定技能1号評価試験 | 〃 | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提 供 |
| 自動車運送業 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験等 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) ※タクシー運転者、バス運転者については日本語能力試験(N3以上) | ・トラック運転者 ・タクシー運転者 ・バス運転者 |
| 鉄道 | 鉄道分野特定技能1号評価試験等 | 〃 ※運輸係員(駅係員、車掌、運転士)については日本語能力試験(N3以上) | ・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 ・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士) |
| 農業 | 1号農業技能測定試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上) | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
| 漁業 | 1号漁業技能測定試験 | 〃 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁 獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・ 処理、安全衛生の確保等) |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | 〃 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保) |
| 外食業 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | 〃 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
| 林業 | 林業技能測定試験 | 〃 | ・林業(育林、素材生産等) |
| 木材産業 | 木材産業特定技能1号測定試験 | 〃 | ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 |
【特定技能2号の対象分野】2025年9月1日現在
※上記特定技能1号の対象分野のうち、以下の分野が対象。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
→出入国在留管理庁HP(pdf)「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
ここで、よく混同されがちな「ビザ」と「在留資格」について、説明をしておきます。
「ビザ(査証)」とは、外国にある日本の大使館や領事館がパスポートをチェックし、日本への入国は問題ないと判断した場合に発給されるもので、日本への入国に関する認定の裏書をさします。ただし、日本への入国にあたってこの「ビザ」は必要なものですが、実際に上陸を許可するか否かは、日本の空港や港で上陸時に行われる上陸審査の際に入国審査官が決定します。入国審査官はパスポートに貼られたビザを確認し、上陸を許可するのであればビザに見合った「在留資格」を付与して外国人を上陸させることになります。その時点で「ビザ」は使用済みとなり、上陸時に与えられた「在留資格」が上陸後の外国人が日本に在留する根拠となります。
また、「ビザ申請」と国内で一般的にいわれるものについては、正確には「在留資格認定証明書交付申請」のことを指します。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する、当該外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合すると判断した証明書をいいます。この証明書を事前に取得し、在外公館でビザ発給を申請する場合、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているとして扱われるため、ビザの発給が迅速に行われることとなります。外国人の入国の大半はこの方式を利用しています。
在留資格認定証明書交付申請は、当該外国人、又は、行政書士、弁護士などの代理人が、当該外国人の居住予定地を管轄する出入国管理局(支局・特定の出張所を含む)に申請書を提出して行います。
ただし、本サイトでは、特に断りの無い限り、「在留資格認定証明書交付申請」については一般的な呼称である「ビザ申請」という言葉で言い表します。
登録支援機関・支援計画とは
特定技能1号ビザ、及び特定技能ビザ2号の概要については、上記で紹介しましたが、そのなかで、特定技能1号ビザで就労する外国人への支援が必要であることについて、ここで少し詳しく紹介しておきます。
特定技能1号ビザを取得し就労する外国人を雇い入れる受入れ機関は、「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(以下、「支援計画」という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
支援の項目は義務的なものでも10項目に及び、雇用主はこれらの支援を実施する義務を負う訳ですが、当該支援業務については、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。2025年9月10日現在10,580機関が登録されています。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます。なお、このみなし適用は、一部の委託の場合には適用されませんので、注意が必要です。一部の委託の場合は、受入れ機関においても特定技能1号外国人への支援の実施体制の整備が必要となります。
一方、特定技能外国人への支援計画書の作成は、受入れ機関が支援を実施する際にも登録支援機関に支援を委託する場合にも受入れ機関が作成する必要があるものです。
また、特定技能1号支援計画は特定技能1号ビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)の添付書類となるため、外国人一人一人について、事前に作成する必要がありますが、支援の実施と並び、特定技能外国人を受け入れる企業にとっては大変な事務的負担となることから、行政書士などの専門家に作成支援を依頼することなども検討されてはいかがかと思います。以下に支援計画の記載項目を紹介しておきます。
【支援計画の義務的支援10項目】
- 事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明 - 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行 - 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助 - 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明 - 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助 - 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等 - 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等 - 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等 - 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供 - 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
なお、支援計画は、日本語及び当該支援計画に係る外国人が十分に理解し得る言語により作成し、当該外国人にその写しを交付しなければなりません。
特定技能ビザ取得の要件
特定技能ビザ取得の要件については、実に多くの要件を充足することが求められ、また、その法令による規定も複雑です。
大きくは、在留資格該当性と上陸許可基準適合性とに分けられ、在留資格該当性においては、①特定産業分野該当性、②業務区分該当性、③受入機関適合性、④契約適合性の要件充足が必要ですが、①及び②については上述のとおりですし、③及び④については、事業者の適正性、契約の適正性が確保されることと理解しておいていただきたいと思います。
ここでは、上陸許可基準適合性について、概要の紹介などで上述した点以外の上陸許可基準省令に規定される特定技能ビザ要件で注意しておいていただきたいものを紹介しておきたいと思います。
- 雇用主との雇用契約において、違約金等の定めがないこと。
- 母国の募集機関・紹介機関に対する費用の支払がある場合、その費用について当該外国人が十分に理解したうえで合意したものであること。
- 特定技能外国人の就労開始後、雇用主側が提供することの対価として食費、居住費等を求める場合、その価額は適正であることを要し、また、外国人本人が十分に理解したうえで合意していること。また、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
- 法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
以上、多くは、適切な雇用契約のもとに丁寧に対応することにより、問題となることは少ない事項が並びますが、最後の項の各産業分野の所管省庁が定める「上乗せ基準」については、細かな要件が設定されていますので、ビザ申請の際には注意が必要です。
特定技能ビザ申請の流れ
特定技能ビザの申請後の審査は平均で1~3か月に及びます。令和7年7月は平均で、1号で平均65日、2号で55日が審査に要されていますので、お急ぎの場合は、専門家に依頼することも検討されることをお勧めします。
流れは以下のとおりです。
支援計画の作成
特定技能ビザにより受け入れる外国人の担う業務を選定し、職場環境の整備を行ったうえ、支援計画を作成します。
登録支援機関との支援委託契約
定技能ビザにより受け入れる外国人の担う業務が特定技能1号に該当する場合、自社で支援を実施するのでなければ、登録支援機関に支援実施を依頼する必要があります。
また、この際に、外国人の募集についての支援が得られるか確認し、支援が得られない場合はあっせん企業などに採用募集手続きを依頼する必要があります。
採用募集~応募~採用決定
応募のあった外国人から採用者を決定し、雇用契約を締結します。
このあと日本国内で行うビザ申請には、支援計画書と雇用契約書の添付が必要となります。
出入国管理局に特定技能ビザ申請
採用する特定技能外国人が住まうこととなる予定住所地を管轄する出入国管理局の窓口で申請します。
申請取次者として出入国管理局の承認を受けた行政書士・弁護士は申請を取り次ぐことができます。
許可
在留資格認定証明書の交付を受け、これを採用外国人に郵送し、当該外国人はこれを添付して現地の日本大使館等で査証の発給を受けます。この査証により外国人は日本に入国できるようになります。
入国~就労、支援
当該外国人の支援は、入国前の事前ガイダンスから始まります。入国後は空港への迎え、日本での生活に関するオリエンテーション等が必要になりますが、入国前に住居を確保しておくことも支援の内容として必要となります。
特定技能ビザ申請に必要な書類
ここでは、特定技能ビザ申請を行う際の必要書類を、以下に一覧で紹介しておきますが、受け入れる産業分野、事業所の規模などにより必要な書類が異なりますので、例としてご覧ください。
特定技能ビザ申請を行う場合に必要な書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm横3cm)
- 返信用封筒
- 特定技能外国人本人に関する書類の例
特定技能外国人の報酬に関する説明書・賃金規程の写し
特定技能雇用契約書の写し
雇用の経緯に係る説明書
健康診断個人票・受診者の申告書
1号特定技能外国人支援計画書
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類(ベトナム、カンボジア国籍の場合) - 受入れ機関(雇用主に関する書類)の例
登録支援機関に支援の全部を委託しない場合、支援責任者と担当者を記載した文書
登記事項証明書
業務執行役員の住民票
労働保険納付証明書
社会保険加入状況回答票
納税証明書(源泉徴収所得税、法人税、消費税)
法人住民税納税証明書(直近1年分) - 介護分野の例
介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
協議会の構成員であることの証明書
最後に
以上、特定技能ビザについて、その内容とビザ申請方法、申請における留意点を解説しましたが、出入国在留管理局に対して行うビザ申請には多くの書類の添付が必要であり、また補足説明資料なども必要となってきます。
一度不許可となると再申請はその分ハードルが上がる傾向にもありますので、ビザ申請に不安がある方は、専門家に相談することも検討されることをお勧めします。
当事務所では、特定技能ビザを申請される企業様のビザ申請を代行する>ビザ申請アウトソーシング及び>外国人雇用スタートアップ・サポートをご用意し、お客様のビザ申請を全面的にサポートするサービスを提供しております。
無料相談にて、永住ビザの許可取得が可能か、また、問題点がある場合にどの程度是正ができるかのアドバイスをさせていただきます。
無料相談は、①電話、②メール、③オンライン(Zoom、Line等)、④来所、⑤ご自宅訪問のいずれかでご対応しております。まずは、お気軽に、お電話かメールでお問合せください。
無料相談はこちら
\
他にご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽に
お問い合わせください!
/

.png)
この記事の執筆者
高知VISAサポートセンター所長
森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士、宅地建物取引士
私も、イギリス在留中には、フラット(アパート)を借りる際をはじめ、多くの現地の方にたくさんお世話になりました。
当事務所では、ビザ申請に関すること以外にも、外国籍の方の行政手続き・不動産・日常生活に関する様々なお困りごとにも相談対応が可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
- 主な担当業務
外国人のお客さまのビザ申請に関するサポートのほか、外国人を雇用する企業様の法的サポートを提供しています。 - Profile
1993年 3月 高知県立追手前高校 卒業
1993年 4月 立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
入管申請取次行政書士(行ー192025200024)
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号