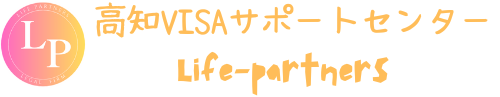一般的にいわれる「配偶者ビザ」とは、正式には、在留資格の「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」を指します。
ここでは、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等が日本で暮らすために必要な「配偶者ビザ」について、どのような場合に取得することができる?、どうやって申請する?、といった疑問にお答えします。

【このページの要点】
- 配偶ビザを申請できるのは、①日本人・永住者の配偶者、②日本人・永住者の子
- 配偶者の要件:①現に婚姻中であること、②双方の国籍国で法的に夫婦であること(内縁は不可)、③同居するなど夫婦としての実体があること
- 配偶者は、海外にいても、日本にいてもビザ申請可能
- 同居してない、夫婦の年齢差がある、離婚歴がある場合は、ビザ申請に注意が必要
- 1. 配偶者ビザとは
- 1.1. 在留資格「日本人の配偶者等」とは
- 1.1.1. 日本人の配偶者
- 1.1.2. 日本人の特別養子
- 1.1.3. 日本人の子として出生した者
- 1.2. 在留資格「永住者の配偶者等」とは
- 1.2.1. 永住者等の配偶者
- 1.2.2. 永住者等の子として日本で出生し、その後、引き続き日本に在留している者
- 2. 配偶者ビザ申請の流れ
- 2.1. 配偶者が海外にいる場合
- 2.2. 配偶者が国内にいる場合
- 3. 配偶者ビザ申請に必要な書類
- 4. 配偶者ビザ申請の審査のポイント(注意すべき事項)
- 4.1. 同居していない場合
- 4.2. 夫婦の年齢差が大きい場合
- 4.3. 離婚歴がある場合
- 5. まとめ
- 6. 無料相談はこちら
配偶者ビザとは
一般にいう「配偶者ビザ」とは、正式には、出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という。)に規定される在留資格の「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」を指します。
ここで、よく混同されがちな「ビザ」と「在留資格」について、説明をしておきます。
「ビザ(査証)」とは、外国にある日本の大使館や領事館がパスポートをチェックし、日本への入国は問題ないと判断した場合に発給されるもので、日本への入国に関する認定の裏書をさします。ただし、日本への入国にあたってこの「ビザ」は必要なものですが、実際に上陸を許可するか否かは、日本の空港や港で上陸時に行われる上陸審査の際に入国審査官が決定します。入国審査官はパスポートに貼られたビザを確認し、上陸を許可するのであればビザに見合った「在留資格」を付与して外国人を上陸させることになります。その時点で「ビザ」は使用済みとなり、上陸時に与えられた「在留資格」が上陸後の外国人が日本に在留する根拠となります。
また、「ビザ申請」と国内で一般的にいわれるものについては、正確には「在留資格認定証明書交付申請」のことを指します。「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する、当該外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合すると判断した証明書をいいます。この証明書を事前に取得し、在外公館でビザ発給を申請する場合、在留資格に関する上陸条件についての法務大臣の事前審査を終えているとして扱われるため、ビザの発給が迅速に行われることとなります。外国人の入国の大半はこの方式を利用しています。
在留資格認定証明書交付申請は、当該外国人、又は、配偶者、行政書士、弁護士などの代理人が、当該外国人の居住予定地を管轄する出入国管理局(支局・特定の出張所を含む)に申請書を提出して行います。
ただし、本サイトでは、特に断りの無い限り、「在留資格認定証明書交付申請」については一般的な呼称である「ビザ申請」という言葉で言い表します。
在留資格「日本人の配偶者等」とは
「日本人の配偶者等」の在留資格には、①日本人の配偶者、②日本人の特別養子、③日本人の子として出生した者が該当します。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した方々は、日本に在留中に行うことのできる就労には制限がありませんので、仕事に就く際にも新たに就労ビザを取得する必要がありません。
また、家族滞在ビザのように、扶養を受けることが要件でないため、日本人夫の方が専業主夫で、外国人妻が就労し夫を扶養するという状況でも日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在することが可能です。
それでは、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得可能な①日本人の配偶者、②日本人の特別養子、③日本人の子として出生した者に、どのような方が該当するのか、個別に見ていきましょう。
日本人の配偶者
在留資格「日本人の配偶者等」における配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。この点については、「永住者の配偶者」及び「家族滞在」においても同様です。
同性婚については、たとえ日本人と同性婚をしている外国人の本国法において同性婚が認められていたとしても、日本国民法が同性婚を認めていない以上法適用の関係から当該外国人と日本人との同性婚は法的に有効な婚姻とされません。また、「永住者の配偶者」及び「家族滞在」においても、平成25年10月18日管在5357号において、「各当事者の本国法により外国で有効に成立した婚姻であっても、同性婚は日本国民法に照らして有効と言えず、在留資格該当性は認められない」旨の解釈が示されています。
日本人の特別養子
特別養子とは、民法第817条の2以下の手続きで家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間で実の親子と同様の関係が成立するものです。このことによって在留資格として認めらており、一般の普通養子は認められないことに注意が必要です。
日本人の子として出生した者
「子」には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。
「日本人」の子という要件に関しては、出生の時に父又は母のいずれかが日本国籍を有していた場合、または、本人の出生前に父は死亡したもののその死亡時に父が日本国籍を有していた場合に要件該当性が認められます。
出生場所には特に制限はなく、外国で出生した場合も認められます。この点が、「本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している」ことが要件とされる在留資格「永住者の配偶者等」と異なります。
本人の出生後、父母が日本国籍を離脱したとしても何ら「日本人の子として出生」したことに影響を与えるものでないことは当然ですが、本人の出生後に父母が日本国籍を取得したとしても本人に在留資格「日本人の配偶者等」が認められることはありません。
在留資格「永住者の配偶者等」とは
「永住者の配偶者等」の在留資格には、①永住者の資格をもって在留する者、若しくは、「平和条約国籍離脱者等入管特例法」に定める特別永住者(以下、「永住者等」という。)の配偶者、②永住者等の子として出生し、その後、引き続き日本に在留している者が該当します。
「永住者の配偶者等」の在留資格を取得した方々は、日本に在留中に行うことのできる就労には制限がありませんので、仕事に就く際にも新たに就労ビザを取得する必要がありません。
また、家族滞在ビザのように、扶養を受けることが要件でないため、永住者等夫の方が専業主夫で、外国人妻が就労し夫を扶養するという状況でも永住者の配偶者等の在留資格で日本に滞在することが可能です。
それでは、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得可能な①永住者等の配偶者、②永住者等の子として日本で出生し、その後、引き続き日本に在留している者に、どのような方が該当するのか、個別に見ていきましょう。
永住者等の配偶者
在留資格「永住者の配偶者等」における配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれません。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。この点については、「日本人の配偶者」及び「家族滞在」においても同様です。
同性婚については、「家族滞在」についても、平成25年10月18日管在5357号において、「各当事者の本国法により外国で有効に成立した婚姻であっても、同性婚は日本国民法に照らして有効と言えず、在留資格該当性は認められない」旨の解釈が示されています。また、「日本人の配偶者等」についても、日本人と同性婚をしている外国人の本国法において同性婚が認められていたとしても、日本国民法が同性婚を認めていない以上法適用の関係から当該外国人と日本人との同性婚は法的に有効な婚姻とされません。
永住者等の子として日本で出生し、その後、引き続き日本に在留している者
「子」には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。
「永住者」の子という要件に関しては、出生の時に父又は母のいずれかが「永住者」の在留資格をもって在留していた場合、または、本人の出生前に父は死亡したもののその死亡時に父が永住者の在留資格をもって在留していた場合に要件該当性が認められます。
なお、この出生時の「在留」については、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国している場合を含みます。
再入国しなかった場合
再入国許可を受けている父が出国後、再入国することなく、当該再入国許可の有効期限が満了したときは、その時点で父は永住者等ではなくなるので、その後に出生した子は、永住者等の子として出生した者とはなりません。
ただし、結果的に父が再入国をしなかった場合でも、再入国をしなかったことによる在留資格の消滅は再入国許可の有効期間の満了により生じるため、再入国許可の有効期間が満了するまでに出生した子は、永住者等の子として出生した者であると解されます。
出生場所については、特に制限のない「日本人の配偶者等」とは異なり、日本での出生に限られます。また、「出生後引き続き」日本に在留することが必要であることから、例えば、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得した後、再入国許可を受けずに単純出国したときは、再度「永住者の配偶者等」の在留資格をもって上陸許可を受けることはできません。
なお、特別永住者の子として日本で出生し、その後、引き続き日本に在留している者については、通常入管特例法第4条の申請を行い、特別永住者として在留することとなります。しかし、申請期限(入管特例法第4条2項により60日)の経過等により同申請が認められない場合には「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されることとなります。この場合、あわせて入管特例法第5条の特別永住許可申請を行うこととなります。
配偶者ビザ申請の流れ
配偶者が海外にいる場合
配偶者が海外に居住している場合には、日本において「在留資格認定証明書交付申請」を出入国管理局に対して行い、交付された証明書を海外の配偶者に送付して、これを添付して在外公館でビザの発給を受けるという手続きが必要になります。
流れは以下のとおりです。
出入国管理局に配偶者ビザ申請
配偶者の入国後の居住予定地を管轄する出入国管理局の窓口で申請します。
日本側の配偶者など、海外側の配偶者の親族で日本に住まう者が代理申請することができます。また、申請取次者として出入国管理局の承認を受けた行政書士・弁護士は申請を取り次ぐことができます。
許可
審査には2~3か月かかることもありますが、許可が下りると、在留資格認定証明書が交付されます。
証明書を海外の配偶者に郵送
出入国管理局から交付された在留資格認定証明書を海外の配偶者に郵送します。
海外の日本大使館に査証申請
日本から郵送された在留資格認定証明書を添付して、海外の配偶者が現地の在外公館に査証の発給を申請します。
査証発給後3か月以内に入国
発給を受けた査証の有効期間は3か月です。この期限までに配偶者は日本に入国する必要があります。
入国
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港の7空港では、上陸許可時に「在留カード」が交付されます。
これら以外の場所で入国した場合には、市区町村で届け出た住居地に簡易書留で「在留カード」が届きます。
※外国人は、入国後14日以内に住居地の届出を市区町村にしなければなりません。
配偶者が国内にいる場合
配偶者がすでに取得している在留資格を変更する手続きが必要となります。
変更許可後、新しい「在留カード」を受け取ります。
配偶者ビザ申請に必要な書類
日本人の配偶者等のビザ申請に必要な書類は以下のとおりです。
日本人の配偶者等ビザ申請添付書類一覧
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人配偶者の写真(縦4cm×横3cm)
※申請前3か月以内に撮影したもの - 日本人配偶者の戸籍謄本
※申請前3か月以内に発行されたもの - 外国人配偶者の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 外国人配偶者の滞在費用を支弁する者の住民税の課税証明書・納税証明書
※申請前3か月以内に発行されたもの - 日本人配偶者による身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
※個人番号は省略し、他の事項については省略の無いもの
※申請前3か月以内に発行されたもの - 出入国在留管理局所定の質問書
※交際経緯や生活状況等説明書(様式自由)も提出したほうが良い - スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工したものは不可)
※渡航記録、通話記録、手紙、メール、LINEをプリントアウトしたもののほか、送金明細など交際や婚姻の実体を証明するための資料も提出した方が良い - 返信用切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載
※外国人配偶者が既に日本にいる場合、在留カードも提出します。
配偶者ビザ申請の審査のポイント(注意すべき事項)
最後に、配偶者ビザを申請する場合、同居していない、夫婦の年齢差が大きいなど、不許可と判断される可能性のある状況について、ここで触れておきたいと思います。
同居していない場合
「日本人の配偶者」または「永住者等の配偶者」として在留資格を取得するためには、法律上有効な婚姻関係にあるというだけでは足りず、婚姻の実体が伴っている必要があります。具体的には、同居し、互いに協力し、扶助し合って社会通念上夫婦と言い得る程度の共同生活が必要であるとされます。
特別な事情の無い限り、婚姻の実体があると言い得るためには同居して生活していることが求められますので、同居していない場合には、別途理由書などを提出し丁寧に事情を説明することが求められます。交流の実態について、スナップ写真のみでなく、通話記録やメールのやり取りなども提出し、頻繁且つ継続的に交流がある旨を立証すべきです。
なお、京都地判平27.11.6では、婚姻生活の多様化に伴い、週に1日のみ同居している事案について在留資格該当性が認められています。
夫婦の年齢差が大きい場合
夫婦の年齢差が大きい場合、婚姻の実体について厳しく審査される傾向にあります。このような場合には、質問書の回答において、交際や婚姻の経緯、婚姻後の生活状況を詳細に述べる必要があるでしょう。
離婚歴がある場合
特に申請者である外国人配偶者側に日本人との離婚歴がある場合や日本人側に外国人との離婚歴がある場合、婚姻の実体について丁寧に説明する必要があります。基本的には、夫婦の年齢差が大きい場合と同様ですが、加えて、前婚の離婚理由等についても説明する必要があるでしょう。
まとめ
以上、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」について、その内容とビザ申請方法、申請における留意点を解説しましたが、出入国在留管理局に対して行うビザ申請には多くの書類の添付が必要であり、また補足説明資料なども必要となってきます。
一度不許可となると再申請はその分ハードルが上がる傾向にもありますので、ビザ申請に不安がある方は、専門家に相談することも検討されることをお勧めします。
当事務所では、配偶者ビザを申請されるお客様のビザ申請を代行する>配偶者・結婚ビザ申請サポートをご用意し、お客様のビザ申請を全面的にサポートするサービスを提供しております。
無料相談にて、配偶者ビザの許可取得が可能か、また、問題点がある場合にどの程度是正ができるかのアドバイスをさせていただきます。
無料相談は、①電話、②メール、③オンライン(Zoom、Line等)、④来所、⑤ご自宅訪問のいずれかでご対応しております。まずは、お気軽に、お電話かメールでお問合せください。
無料相談はこちら
\
他にご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽に
お問い合わせください!
/

.png)
この記事の執筆者
高知VISAサポートセンター所長
森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士、宅地建物取引士
私も、イギリス在留中には、フラット(アパート)を借りる際をはじめ、多くの現地の方にたくさんお世話になりました。
当事務所では、ビザ申請に関すること以外にも、外国籍の方の行政手続き・不動産・日常生活に関する様々なお困りごとにも相談対応が可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
- 主な担当業務
外国人のお客さまのビザ申請に関するサポートのほか、外国人を雇用する企業様の法的サポートを提供しています。 - Profile
1993年 3月 高知県立追手前高校 卒業
1993年 4月 立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
入管申請取次行政書士(行ー192025200024)
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号