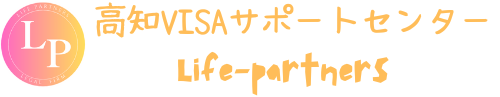帰化は、日本の国籍を取得し日本国民となるという点において、母国の国籍を有しながら日本で暮らす各種在留資格とは異なる制度です。
ここでは、帰化申請をどのような場合に行うことができる?、どうやって申請する?、といった疑問にお答えします。

【このページの要点】
- 帰化要件:①日本に5年以上在住、②18歳以上であり本国でも成人、③素行良好、④生計を営めること、⑤帰化の際に本国の国籍離脱が可能、⑥日本国政府破壊を企ててないこと、⑦日常的な日本語能力
- 帰化要件が緩和される場合があります。(9類型)
- 帰化申請に必要な書類:①作成書類、②国内収集書類、③母国での収集書類
- 帰化申請の流れ
- 1. 帰化とは
- 2. 帰化についての6つの要件と日本語力
- 2.1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 2.2. 18歳以上で本国で成人にあたること
- 2.3. 素行が善良であること
- 2.4. 生計を営むことができること
- 2.5. 無国籍又は日本国籍を取得することで母国の国籍を失うべきこと
- 2.6. 日本政府を破壊する企てを有しないこと
- 2.7. 日本語能力
- 3. 簡易帰化の要件
- 3.1. 日本国民の子(養子を除く。)で3年以上日本に住所・居所を有するもの
- 3.2. 日本で生まれた者で3年以上日本に住所・居所を有するもの、父又は母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 3.3. 10年以上日本に居所を有する者
- 3.4. 日本人の配偶者で3年以上日本に住所・居所を有し、現に住所を有するもの
- 3.5. 日本人の配偶者で婚姻から3年を経過し、1年以上住所を有するもの
- 3.6. 日本人の子(養子を除く。)で住所を有するもの
- 3.7. 日本人の養子で1年以上日本に住所を有し、縁組の時未成年であつたもの
- 3.8. 日本の国籍を失つた者で住所を有するもの
- 3.9. 日本で生まれた無国籍者で、3年以上住所を有するもの
- 4. 帰化のメリット
- 4.1. 選挙権・被選挙権が付与される
- 4.2. 再入国許可が不要になる
- 4.3. 戸籍が編製される
- 4.4. 就労に関する制限がなくなる
- 4.5. ビザなし渡航できる国が多い
- 5. 帰化申請の流れ
- 6. 帰化申請に必要な書類
- 6.1. 帰化申請のために自分で作成する書類
- 6.2. 帰化申請のために国内で収集すべき書類
- 6.3. 帰化申請のために母国から取り寄せるべき書類
- 7. まとめ
- 8. 無料相談はこちら
帰化とは
帰化とは、他の国の国籍を有する者、又は無国籍の者自らの国籍付与の申し出により、申し出を受けた国家がこれに許可を与えることによって国籍を付与する制度をいいます。
日本では、国籍法第4条第2項の規定により、その許可又は不許可の決定は法務大臣の権限とされます。
国籍法(抜粋)
(帰化)
第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
また、重国籍を容認する国もみられますが、日本では、国籍法第5条第1項第5号には重国籍の防止条項が存在し、日本国籍保有者が重国籍であることを容認していません。
よって、帰化申請が許可された際には、原則として、現在保有している外国籍をすべて喪失し、日本国籍のみを保有する状況とする必要があります。
帰化についての6つの要件と日本語力
帰化申請を許可するかどうかは、法務大臣の自由裁量行為とされていますが、国籍法第5条第1項に原則的な要件が規定されており、また、国籍法第6条から第9条にはこれらの原則的要件を緩和する場合の規定が定められています。
ここでは、主に、原則的要件と日本語力について解説します。
国籍法(抜粋)
(帰化)
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
引き続き5年以上日本に住所を有すること
国籍法第5条第1項第1号にいう「引き続き」とは、申請者が帰化申請する時から遡って5年間、日本に継続して居住していたかどうかという点について定めるものです。
ただし、5年の間に海外に出国していたすべての場合に期間継続が中断するというものではなく、日本を出国していた期間が連続して3か月以上なく、且つ、年間100日以上でなければ特に問題となることはありません。ただし、この基準は公表されている基準ではないため、あくまで目安としてここで紹介しておきます。
上記の日数を超えて日本を離れた場合、多くの場合は「引き続き」日本に居住したこととは認められず、在留期間に中断があったものと扱われます。この場合は、改めて中長期滞在できる在留資格をもって日本に居住を開始した日から、5年間の期間を要することとなります。
また、単に5年間の居住で足りるわけでなく、うち3年間は技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格をもって就労・居住していることが必要であるというのが、法務局での取扱いとなっています。就労形態の別に関しては、正社員、契約社員、派遣社員等であれば安定した身分として認められますが、アルバイト等での就労はここでの3年間の就労とは認められないことに注意が必要です。
原則としては、上述のとおり、5年間の居住と3年間の就労が必要ですが、国籍法第6条第1項第3号では、「引き続き10年以上日本に居所を有する者」については、要件緩和の可能性のある場合として規定されており、この場合、1年程度の就労の実績があれば、許可の可能性があるといえます。
18歳以上で本国で成人にあたること
日本での成人年齢は18歳であることから申請時点において18歳以上であることが規定されています。
また、本国でも成人に達していることが必要であり、国によって成人年齢が異なることから本国法を確認することが必要です。インドネシアやシンガポールでは21歳が成人年齢であり、アメリカは州ごとに異なります。
なお、18歳未満であっても、親と同時申請する場合などは、例外的に申請可能な場合があります。
素行が善良であること
税金や社会保険料の納付状況、交通違反や犯罪歴の状況について審査が行われます。帰化申請をする際に税金や社会保険料に滞納がある場合は、極力その納付を行うようにしましょう。
生計を営むことができること
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができることが要求されます。これは端的にいえば、一家で生活をやっていけるかという点が帰化申請の際に審査されます。一般的には年収300万円ということがいわれますが、扶養家族が多い場合はその分収入も必要となってきますので、審査基準としてはハードルが上がるということになります。
しかし、この収入要件を気にしすぎて、預金額を増やしておこうと、親族などから借金するようなことはお勧めできません。審査の際に、不自然な金銭の流れとしてマネーロンダリングなどを疑われてしまうと逆効果となります。
無国籍又は日本国籍を取得することで母国の国籍を失うべきこと
日本は重国籍を容認していないため、帰化が認められた際には元の国籍を失うことができることが要件とされています。
日本政府を破壊する企てを有しないこと
日本国政府を暴力をもって妥当することを企てる者、あるいはそれを主張する団体を結成又は加入したことがある者は帰化が許可されることはないのが原則です。具体的にはテロリストなどです。
日本語能力
国籍法に規定はありませんが、帰化には日本語の能力が求められます。日常生活において日本人としての暮らしが営める程度の日本語能力が必要です。
帰化申請後に行われる審査官との面接の際に、日本語のペーパーテストが実施される場合があります。日本語で日常的な読み書きができる程度のレベル、小学校3~4年生程度の日本語能力が必要です。日本語能力検定でいうとN3~N4相当です。
簡易帰化の要件
帰化のための一般的な要件をみてきましたが、ここでは、日本と所縁がある方について、国籍法第6条以下で緩和される要件を紹介します。
日本国民の子(養子を除く。)で3年以上日本に住所・居所を有するもの
例えば、外国で生まれて外国籍を取得しその際に日本国籍を留保しなかった者や、外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した人の子などが該当します。
引き続き日本に5年以上住所(生活の本拠をいう。)を有することとする要件が緩和され、住所又は居所(生活の本拠でなくとも居住する場所で足りる。)を引き続き3年以上日本に有していることで足りるようになります。
日本で生まれた者で3年以上日本に住所・居所を有するもの、父又は母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
日本で生まれた者については、引き続き日本に5年以上住所を有することとする要件が緩和され、住所又は居所を引き続き3年以上日本に有していることで足りるようになります。
また、父母のいずれかが日本で生まれている場合のその子については、居住要件が免除されます。
10年以上日本に居所を有する者
引き続き日本に5年以上住所を有することとする要件が緩和され、日本に10年間居所を有したことで足りるようになります。また、上述のとおり、就労要件についても3年が1年に緩和されるので実務上の取扱いです。
日本人の配偶者で3年以上日本に住所・居所を有し、現に住所を有するもの
日本人の配偶者として引き続き3年間日本に住所又は居所を有する者については、現に日本に住所を有する限り、引き続き日本に5年以上住所を有することとする要件が緩和され、また、帰化申請時に18歳以上かつ本国で成人に達していなければならないという要件が免除されます。
日本人の配偶者で婚姻から3年を経過し、1年以上住所を有するもの
日本人の配偶者となって3年が経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する者については、引き続き日本に5年以上住所を有することとする要件が緩和され、また、帰化申請時に18歳以上かつ本国で成人に達していなければならないという要件が免除されます。
日本人の子(養子を除く。)で住所を有するもの
帰化申請時に父母のいずれかが日本国籍であるか、帰化申請時に死亡していたとしてもその死亡当時に日本国籍であれば、その子は、帰化申請時に日本に住所を有する限り、5年以上の住所要件、18歳以上かつ本国法成人要件、生計要件が免除されます。
なお、日本人の両親の間に生まれた子であっても、海外で生まれた場合、出生後3か月以内に在外公館に届出をしない場合には日本の戸籍に日本人の子として記載されないため注意が必要です。この届出が抜かってしまうと、本項の簡易帰化要件を使って帰化申請が必要になってしまいます。
日本人の養子で1年以上日本に住所を有し、縁組の時未成年であつたもの
日本人が未成年の外国人を養子とした場合や、養子縁組をしたときには養親が外国籍であったが、後に養親のみが日本国籍を取得した場合などに適用が考えられます。引き続き1年以上日本に住所を有する限り、5年以上の住所要件、18歳以上かつ本国法成人要件、生計要件が免除されます。
日本の国籍を失つた者で住所を有するもの
若いころに外国籍を取得し海外で生活していたが、日本に帰国したという場合などに適用が考えられます。帰化申請時点で日本に住所を有する限り、5年以上の住所要件、18歳以上かつ本国法成人要件、生計要件が免除されます。
なお、日本に帰化した後に日本の国籍を失つた者は対象外です。
日本で生まれた無国籍者で、3年以上住所を有するもの
両親が外国籍で、その子が日本で出生したが、どちらの国籍も取得しないで無国籍となった場合などに適用が考えられます。帰化申請時点で引き続き3年以上日本に住所を有する限り、5年以上の住所要件、18歳以上かつ本国法成人要件、生計要件が免除されます。
無国籍者の救済が趣旨といえます。
帰化のメリット
帰化申請が許可され日本国籍を付与された場合に得られる主なメリットを紹介します。
選挙権・被選挙権が付与される
日本国籍を取得し、国民の権利として当然に保障される参政権を得ることができます。投票することも、選挙に出馬することも可能になります。
再入国許可が不要になる
永住ビザでは必要になる出国の際の「再入国許可」や「みなし再入国許可」が不要になります。また、「強制退去」などの処分を心配する必要もなくなります。
戸籍が編製される
外国籍の場合、日本人と婚姻したときには、日本人配偶者の戸籍の婚姻の欄に配偶者として記載されますが、自分の戸籍が編製されることはありません。帰化により日本国籍を取得した場合、自分の戸籍が編製されることとなります。
就労に関する制限がなくなる
身分に基づく在留資格を有していない方は、帰化が認められることにより就労に関する制限が無くなります。
ビザなし渡航できる国が多い
観光で海外へ渡航する場合、ビザなしで渡航できる国が非常に多いのが日本です。
帰化申請の流れ
帰化申請では、ビザ申請と異なり、申請者本人が法務局の窓口に申請する必要があります。
しかし、大変多くの書類を必要とする手続きであるため、申請書作成について専門家に相談することもお勧めします。
流れは以下のとおりです。審査期間は1年以上に及びます。
法務局への相談
法務局の帰化相談は完全予約制となっており、電話で日時を予約する必要があります。法務局での事前相談は複数回に及ぶことが一般的で、必要書類をすべてそろえることができて申請を行います。
法務局に帰化申請
必要書類を添付して帰化申請書を提出します。
審査・面接
申請受付後、1人の審査官が担当することとなります。数か月経過すると、この審査官から面接の呼び出しがあるので、対応しましょう。
法務省での審査
面接終了後、管轄の法務局の審査会で審査が行われた後、申請は本省に送られ、本省審査が行われます。
許可
めでたく許可が下りると、担当の審査官から連絡がきます。
帰化申請に必要な書類
帰化申請に必要な書類には、①申請者が作成すべき書類、②日本国内で収集すべき書類、③母国から取り寄せるべき書類があります。
以下、それぞれについて一覧で紹介します。
帰化申請のために自分で作成する書類
手書きで作成する場合は、誤って記載した部分は修正テープなどで消すことはできず、二重線を引いて余白に記入するなどの作業が必要になりますので、鉛筆で下書きしたうえ、法務局で審査官に確認してもらったうえ、ボールペンで清書するようにしましょう。
申請者が作成すべき書類一覧
- 帰化許可申請書(正本・副本)
※正本・副本それぞれに6か月以内に撮影した証明写真(5cm×5cm)の貼付が必要です。 - 親族の概要(日本)
※日本在住の親族の状況を記載します。 - 親族の概要(海外)
※海外在住の親族の状況を記載します。 - 履歴書その1
※出生以降の居住歴・学歴・職歴を記入します。 - 履歴書その2
※出入国歴、技能・資格、本国での使用言語、賞罰を記入します。
※日本人配偶者がいる場合は直近1年分、その他最大直近5年分の出入国記録の記載が必要です。 - 生計の概要その1
※自身及び生計を同じくする親族の収入の状況を記載します。 - 生計の概要その2
※自身及び生計を同じくする親族の国内及び国外の資産の状況を記載します。 - 事業の概要
※自身又は生計を同じくする親族が事業を営んでいる場合に作成が必要です。 - 自宅付近の地図
- 勤務先付近の地図
- 在勤及び給与証明書
※自身又は生計を同じくする親族が勤務先から収入を得ている場合に提出が必要です。
※勤務先の会社に証明してもらいます。 - 帰化の動機書
※帰化したいと思ったきっかけ、帰化したい理由、帰化して行いたいことなどを記載します。
※原則として、申請者の自書が必要な書類です。 - 申述書
帰化申請のために国内で収集すべき書類
帰化申請のために国内で収集すべき書類については、身分関係、収入、税金に関するものなど、個々の事例によって異なりますが、ここでは、必要となる可能性の高い書類を紹介しておきます。
国内で収集すべき書類一覧
- 住民票
※マイナンバーは省略可能です。 - 戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票
※親族のなかに日本人や帰化した者がいる場合に必要になります。 - 記載事項証明書(出生、婚姻、離婚、死亡等)
※日本の役所に出生、婚姻、離婚、死亡等の届出をしたことがある場合に必要となります。届出の際に添付されていた書類も必要です。 - 住民税の課税証明書・納税証明書
※同居の親族に収入のある場合、その親族のものも必要となります。 - 所得税の納税証明書
※同居の親族に収入のある場合、その親族のものも必要となります。 - 不動産登記事項証明書
※資産の証明として、同居の親族の所有するものも必要となります。 - 会社の登記事項証明書・閉鎖登記事項証明書
※会社を経営している場合に必要です。
※同居の親族が会社を経営している場合には、その会社のものも必要となります。 - 会社の法人都道府県民税・市町村民税の納税証明書
※同居の親族が会社を経営している場合には、その会社のものも必要となります。 - 会社の法人税・消費税・法人事業税の納税証明書
※資本金1千万円未満の法人の場合、前々年の課税売上高が1千万円超の場合に提出が必要となります。
※同居の親族が会社を経営している場合には、その会社のものも必要となります。 - 個人事業の場合の消費税の納税証明書(直近3年分)、個人事業税の納税証明書(直近3年分)
※消費税の納税証明書は、前々年の課税売上高が1千万円超の場合に提出が必要となります。
※同居の親族が事業をしている場合には、その者のものも必要となります。 - 社会保険料納入証明書
※会社経営や個人事業主の場合に提出必要となります。同居の親族が事業を営む場合も提出が必要です。 - 被保険者記録照会回答票
※ねんきん定期便をなくした場合、同居の親族のものも提出が必要です。 - 運転記録証明書(過去5年分)
※運転免許を持っている方は提出が必要です。
※自動車安全運転センターで取得します。
帰化申請のために母国から取り寄せるべき書類
国籍や個々の事例によって母国から取り寄せるべき書類はかわりますが、基本的には身分を証する書類です。
出生を証する書類などは、国によっては一生に1度しか発行されないなどの場合がありますので、注意が必要です。
以下、台湾、韓国、中国の方について紹介します。
【台湾出身の方】
台湾の戸籍制度は、日本の戸籍と住民登録が一緒になったような制度であり、戸長が管外移転するたびに新たな戸籍作成されます。台湾内のどこの戸制事務所であっても戸籍謄本・除籍謄本の取得が可能です。
台湾出身の方が母国から取り寄せるべき書類一覧
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
【韓国出身の方】
韓国の戸籍制度は、2008年1月から家族関係登録制度に制度変更されましたが、以前の戸籍情報については除籍謄本として取得が可能であり、日本における本籍地にあたる「登録基準地」が分かれば、遡って各種身分証明書類を取得することができます。
韓国出身の方が母国から取り寄せるべき書類一覧
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
- 除籍謄本
【中国出身の方】
中国における身分関係の証明書発行所は「公証処」といいます。日本おける公証役場のような役割を担っており、中国には戸籍制度がないことから、各種身分関係を「公証処」で証明してもらうこととなります。
中国出身の方が母国から取り寄せるべき書類一覧
- 出生公証書
- 養子公証書
- 婚姻公証書
- 離婚公証書
- 親族関係公証書
- 死亡公証書
まとめ
以上、帰化申請の手続きについて、その内容と申請方法、添付書類における留意点を解説しましたが、法務局に対して行う帰化申請には多くの書類の添付が必要であり、また何度も平日に足を運ぶことなども必要となってきます。
一度不許可となると再申請はその分ハードルが上がる傾向にもありますので、帰化申請に不安がある方は、専門家に相談することも検討されることをお勧めします。
当事務所では、帰化申請されるお客様の申請書類の作成を代行する>帰化申請サポートをご用意し、お客様の帰化申請を全面的にサポートするサービスを提供しております。
無料相談にて、帰化の許可取得が可能か、また、問題点がある場合にどの程度是正ができるかのアドバイスをさせていただきます。
無料相談は、①電話、②メール、③オンライン(Zoom、Line等)、④来所、⑤ご自宅訪問のいずれかでご対応しております。まずは、お気軽に、お電話かメールでお問合せください。
無料相談はこちら
\
他にご不明な点がありましたら、
どうぞお気軽に
お問い合わせください!
/

.png)
この記事の執筆者
高知VISAサポートセンター所長
森本 拓也
TAKUYA MORIMOTO
行政書士ライフパートナーズ法務事務所
代表行政書士、宅地建物取引士
私も、イギリス在留中には、フラット(アパート)を借りる際をはじめ、多くの現地の方にたくさんお世話になりました。
当事務所では、ビザ申請に関すること以外にも、外国籍の方の行政手続き・不動産・日常生活に関する様々なお困りごとにも相談対応が可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
- 主な担当業務
外国人のお客さまのビザ申請に関するサポートのほか、外国人を雇用する企業様の法的サポートを提供しています。 - Profile
1993年 3月 高知県立追手前高校 卒業
1993年 4月 立命館大学産業社会学部 入学
イギリス留学を経て、行政書士資格取得後公務員として約20年勤務した後、行政書士ライフパートナーズ法務事務所開設。
入管申請取次行政書士(行ー192025200024)
宅地建物取引士登録番号(高知)第005010号